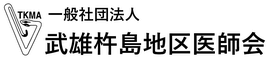武雄杵島地区において設定した『4つの場面の目指すべき姿』について
武雄杵島地区(武雄市・大町町・江北町・白石町)では、令和6年7月から9月にかけて、在宅医療と介護の連携に関する4つの場面(①日常の生活療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取り)について、現状を把握するための調査を、管内の医療・介護関係機関を対象に実施しました。この調査結果をもとに、武雄杵島地区における「4つの場面の目指すべき姿」を設定しましたので、以下①~④に示します。
ちなみに、在宅医療・介護連携推進事業全体の目指すべき姿は下記のとおりです。
「いつでもどこでも切れ目なく必要な医療と介護を受けられる地域の実現」
①.日常の療養支援の目指すべき姿
医療・介護に携わる多職種がそれぞれの専門性を活かして連携し、信頼関係を基盤に情報を共有することで、本人・家族の日常の療養生活を支え、本人が希望する場所で安心して生活できる。
<定めた理由>
多職種がそれぞれの専門性を活かして連携するためには、他職種の業務を理解し、顔の見える関係(信頼関係)を構築することが不可欠である。また、ICT(情報共有システム)の活用を含め、多職種が日常的に情報共有を行うことで、医療や介護のケアにとどまらず、本人・家族の意向を共有し、安心して生活できる支援体制を実現していくため。
②.入退院支援の目指すべき姿
入退院時に携わる医療機関・介護事業所等が、適切なタイミングで情報を共有し、連携を行い、本人が希望する場所で安定的に生活を継続できる。
<定めた理由>
入退院に際して、医療機関・介護事業所等が適切なタイミングで情報共有を行うことは、入院中のケアの充実や、退院後の円滑なサービス調整につながる。また、ICT(情報共有システム)の活用を含め、退院後も入院先とかかりつけ医、ケアマネジャーなどの多職種が定期的に情報を共有し、連携を継続することで、必要な支援が途切れることなく提供され、本人が安心して在宅生活を続けられる体制が整うため。
③.急変時の対応の目指すべき姿
本人や家族の意思を把握し、多職種間で情報を共有することで、急変時にも円滑な連携・本人の意思を尊重した対応ができる。
<定めた理由>
高齢者にとって、急変や緊急対応は避けられず、適切な判断と迅速な対応が求められる。そのため、日常的な関わりの中で本人の意思を汲み取り、本人や家族とともに人生会議(ACP)を実施することが重要である。多職種に加え、消防(救急)とも連携し、事前に意思を共有することで、急変時にも本人の希望に沿った対応が可能となり、不安なく支援を受けられる体制が整うため。
④.看取りの目指すべき姿
多職種と地域住民が人生会議(ACP)についての理解を深め、本人や家族の意思を把握し、随時見直しながら情報を共有することで、本人が望む場所で最期まで安心して過ごせるよう支援し、本人や家族が満足できる。
<定めた理由>
人生の最終段階における生活の質(QOL)を向上させるためには、地域住民が元気なうちから人生会議(ACP)を理解し、多職種がその支援を適切に行うための対応スキルを向上させ、体制を整えることが重要である。看取りの場面では、本人が安心して過ごせることが、家族の精神的負担の軽減につながり、納得のいく別れを迎えることにもつながる。そのため、地域全体でACPの理解を深め、多職種が連携して支援できる体制の構築が求められるため。
今後は、それぞれの場面で設定した「目指すべき姿」の実現に向けて、事業を推進してまいります。引き続き、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。